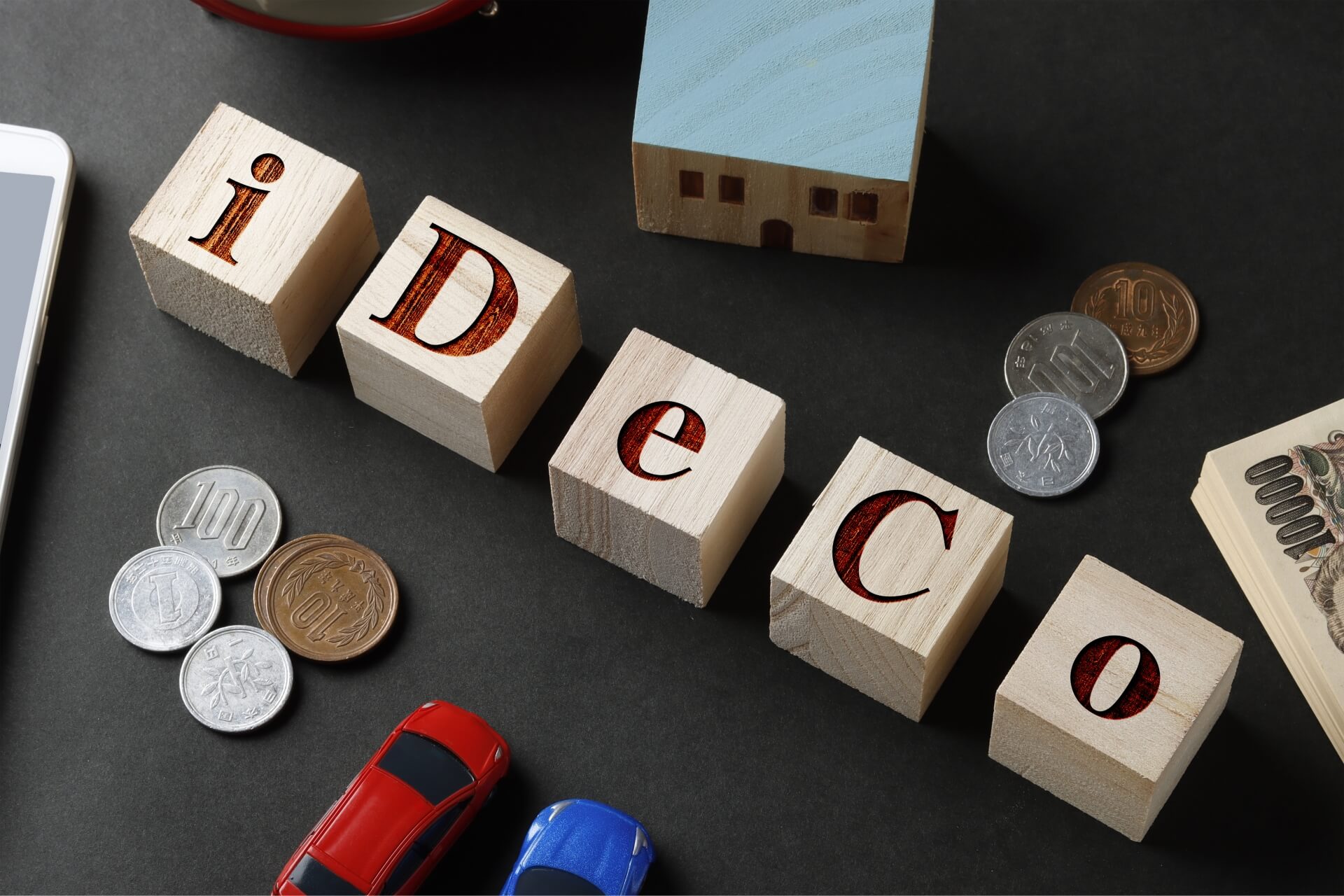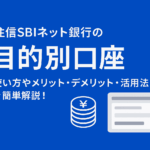「老後資金づくりの切り札」と言われるiDeCo(個人型確定拠出年金)。
2024年12月の制度改正によって、加入できる人の幅が広がり、掛金の上限額も大きく変わります。
今回は、改正点を分かりやすく整理しつつ、「どう活用すれば得になるのか?」を筆者の体験も交えて解説します。
老後資産づくりに不安を感じている方や、「iDeCoって聞いたことはあるけどよく分からない」という方にもおすすめの記事です。
iDeCo(イデコ)ってそもそも何?
まず改正内容に入る前に、基本をおさらいしておきましょう。
iDeCoとは、自分で積み立てた掛金を運用して、将来の年金として受け取れる制度です。
最大のメリットは 税制優遇。掛金は全額所得控除、運用益は非課税、受け取るときも税制上の控除があるという“三段階の節税”が魅力です。
私自身も30代からiDeCoを始めましたが、毎年の年末調整で控除証明書を提出すると、住民税・所得税が下がっているのを実感します。
「貯金するだけで節税になる」って、かなりお得なんですよね。
2024年12月からの主な改正点
1. 掛金拠出限度額の引き上げ
これまでは、企業年金に加入している会社員や公務員の場合、月額1.2万円までしか拠出できませんでした。
改正後は、最大2万円まで拠出可能に!
▶ 例:月1.2万円→2万円にアップ
年間では14.4万円から24万円に増加します。
節税効果も大きくなり、たとえば所得税率20%の方なら、年間約1.9万円の節税額がアップする計算になります。
2. 加入可能年齢が「65歳未満 → 70歳未満」に拡大
これまでは64歳までに加入しないとアウトでしたが、70歳未満まで延長されました。
「定年後も働きたい」「ゆとりある老後資金を作りたい」という人にとって大きなチャンスです。
私の知り合いの経営者も「60代からiDeCoを始めたい」と言っていたので、この改正をとても喜んでいました。
3. 事業主証明書の提出義務が廃止
以前は、会社員や公務員がiDeCoに加入する際に「事業主証明書」が必要でした。
この一枚の紙をもらうのが意外とハードルで、「人事に言いづらい」「書類が戻ってこない」という声も多かったんです。
今回の改正で 証明書は不要に。
加入手続きが一気にラクになります。これで「会社に知られたくないからやめておこう」という人も減りそうです。
4. 掛金拠出方法の変更
注意点もあります。
企業年金など他の制度に加入している人は、iDeCoの掛金は毎月定額のみになります(年単位拠出は不可)。
つまり、「ボーナス月にまとめて拠出したい」というやり方はできなくなります。
ただ、毎月コツコツ積み立てる方がドルコスト平均法の効果も出やすいので、長期投資にはむしろプラスかもしれません。
5. 脱退一時金の受給要件が変更
従来より柔軟に「脱退一時金」が受け取れるようになりました。
たとえば転職や一時的に収入が減った場合など、条件を満たせば従来より受け取りやすくなります。
iDeCo(イデコ)2024年12月改正ポイント比較表
| 項目 | 現行制度 | 改正後(2024年12月~) | ポイント |
|---|---|---|---|
| 加入年齢 | 65歳未満 | 70歳未満まで拡大 | 長く働く人・セカンドライフ準備に有利 |
| 受給開始年齢 | 60歳~75歳 | 60歳~80歳 | 受け取り時期を柔軟に選べる |
| 受給開始の繰下げ | 最大75歳まで | 最大80歳まで | 公的年金の繰下げと合わせやすい |
| 企業型DCとの併用 | 制限あり(条件次第で加入不可) | 原則、企業型DC加入者もiDeCoに同時加入可能 | 会社員の利用が広がる |
| 拠出限度額(会社員) | 月2万円(企業型DCがある場合) | 最大2万円(企業型DCの拠出額により調整) | ダブル活用可能に |
| 受給方法 | 一括受取 / 分割受取 | 一括 / 分割 / 併用可(従来通り) | 大きな変更なし |
職種ごとの掛金上限(2024年12月改正後)
| 職種・立場 | 月額上限 | 年額上限 | 補足ポイント |
|---|---|---|---|
| 自営業者(第1号被保険者) | 68,000円 | 816,000円 | 国民年金基金や付加年金との合算枠 |
| 会社員(企業年金なし) | 23,000円 | 276,000円 | フルに拠出可能 |
| 会社員(企業型DCのみ加入) | 20,000円 | 240,000円 | 企業型DCの事業主掛金額によって調整あり(上限2万円) |
| 会社員(DB+企業型DC加入) | 12,000円 | 144,000円 | 両制度併用の場合は制限あり |
| 会社員(DBのみ加入) | 12,000円 | 144,000円 | 確定給付型年金がある場合 |
| 公務員 | 12,000円 | 144,000円 | 共済年金加入者も同様 |
| 専業主婦(第3号被保険者) | 23,000円 | 276,000円 | 主婦・主夫もフル活用可能 |
メリット
- 節税効果がさらに大きくなる
- 加入できる期間が延び、資産形成のチャンス増
- 書類の手間が減って申込みやすい
注意点
- 他制度加入者は「年単位拠出」ができなくなる
- 年齢上限が延びても「受給開始年齢」には影響なし(要注意)
筆者の考察:改正で「始める人」が増える
今回の改正で一番大きいのは、「ハードルが下がった」という点です。
年齢の制限も、手続きの煩雑さも、そして掛金の上限も改善されました。
実際に私は周囲から「iDeCoを始めたいけど面倒そう」という声をよく聞いていました。
でも、この改正で「やってみよう」と一歩踏み出す人が増えるはずです。
逆に「まだ様子を見ようかな」と思っていると、数年後に「あの時からやっておけば…」と後悔する可能性も高いでしょう。
iDeCo最新改正で得をする人
-
50歳以上の人
→ 加入可能年齢が65歳まで延長されるため、これまで対象外だった層も利用できる。 -
フリーランス・自営業の人
→ 拠出限度額が増え、老後資産形成をより有利に進められる。 -
企業型確定拠出年金に加入している会社員
→ iDeCoとの併用ルールが緩和され、両方を効率的に利用できる。 -
老後の税制メリットを活用したい人
→ 掛金全額が所得控除になるため、所得税・住民税を節税しながら資産形成が可能。
iDeCo最新改正で注意が必要な人
-
拠出余力が少ない人
→ 月々の掛金が生活費を圧迫すると本末転倒。改正で枠が広がっても無理のない範囲が重要。 -
短期間で資金が必要になる可能性がある人
→ iDeCoは60歳まで引き出せないため、急な出費には不向き。 -
投資リスクを理解していない人
→ 掛金は元本保証ではなく、運用次第で元本割れのリスクもある。 -
節税効果が小さい人(収入が少ない人)
→ 所得控除の恩恵が少なく、iDeCoより「つみたてNISA」などの方が適している場合も。
iDeCoとNISAで迷っている・・・
iDeCoの改正はわかったけど、「NISAも気になっている・・・」という方も多いかと思います。そこで筆者なりのポイントを
- 老後まで絶対に使わない、使わないようにしたいという方は → iDeCo
- 投資はしたいけど資金拘束はないほうが良いという方は → NISA
- 今現在の税制優遇を受けたいというかたは → iDeCo
- 投資の利益だけ非課税にしたいという方は → NISA
こんな基準で決めるのも良いかと思います。どうしても迷ってしまうという方はNISAの非課税枠1800万全てを使い切ってからiDeCoで投資を始めるか、iDeCoとNISAの両方にリスク許容度の範囲で少額ずつ投資するのも良いでしょう。
NISAとiDeCoの特徴と違い
| 項目 | NISA | iDeCo |
|---|---|---|
| 目的 | 投資の利益を非課税に | 老後資金のための積立 |
| 非課税対象 | 運用益・分配金 | 運用益 + 掛金が所得控除 |
| お金を引き出せるタイミング | いつでも可能 | 原則60歳以降まで不可 |
| 税制メリット | 運用益が非課税 | 掛金が全額所得控除+運用益非課税 |
| 柔軟性 | 高い(途中売却・出金OK) | 低い(長期固定) |
| 向いている人 | 資産形成を柔軟にしたい人 | 老後資金をしっかり準備したい人 |
iDeCoをやるなら楽天証券、SBI証券
iDeCoを始めるなら、やはり 楽天証券 と
SBI証券
が2大候補になります。
なぜなら、この2社は「運営管理手数料が無料」で「低コストの投資信託が豊富」に揃っているからです。
特に人気が高いのは、
-
楽天証券 … 楽天カード払いで投資信託を積立てるとポイントが貯まるなど、楽天経済圏との相性が抜群。楽天市場や楽天モバイルを利用している人におすすめ。
-
SBI証券 … 業界最大級のラインナップを誇り、eMAXIS Slimシリーズなど信託報酬が安い商品が充実。幅広い選択肢から選びたい人におすすめ。
どちらもiDeCo利用者の満足度が高く、初心者から経験者まで安心して利用できる証券会社です。
「これからiDeCoを始めたいけど、どこで口座を作るのが正解?」と迷ったら、まずはこの2社をチェックしてみましょう。
まとめ:今こそiDeCoを活用すべきタイミング
2024年12月の改正は、働く世代・定年後の人、どちらにもメリットがあります。
✅ 掛金の上限アップで節税効果増
✅ 70歳未満まで加入可能に
✅ 手続きがシンプルに
老後資金づくりは「時間を味方につけること」が最も大切です。
まだ始めていない人は、この制度改正をきっかけに動き出すのがおすすめです。
筆者の結論としては、
「iDeCoもNISAも早く始めるほど得をする。迷うくらいなら小額からでも始めるべき」
ということです。
参考
-
加入可能年齢の拡大(65歳未満 → 70歳未満): 朝日新聞 朝日新聞資産運用はじめるならマネイロ
-
制度全体の概要改正内容: Freee スモールビジネスを世界の主役に フリー株式会社 、三井住友信託銀行 七十七銀行