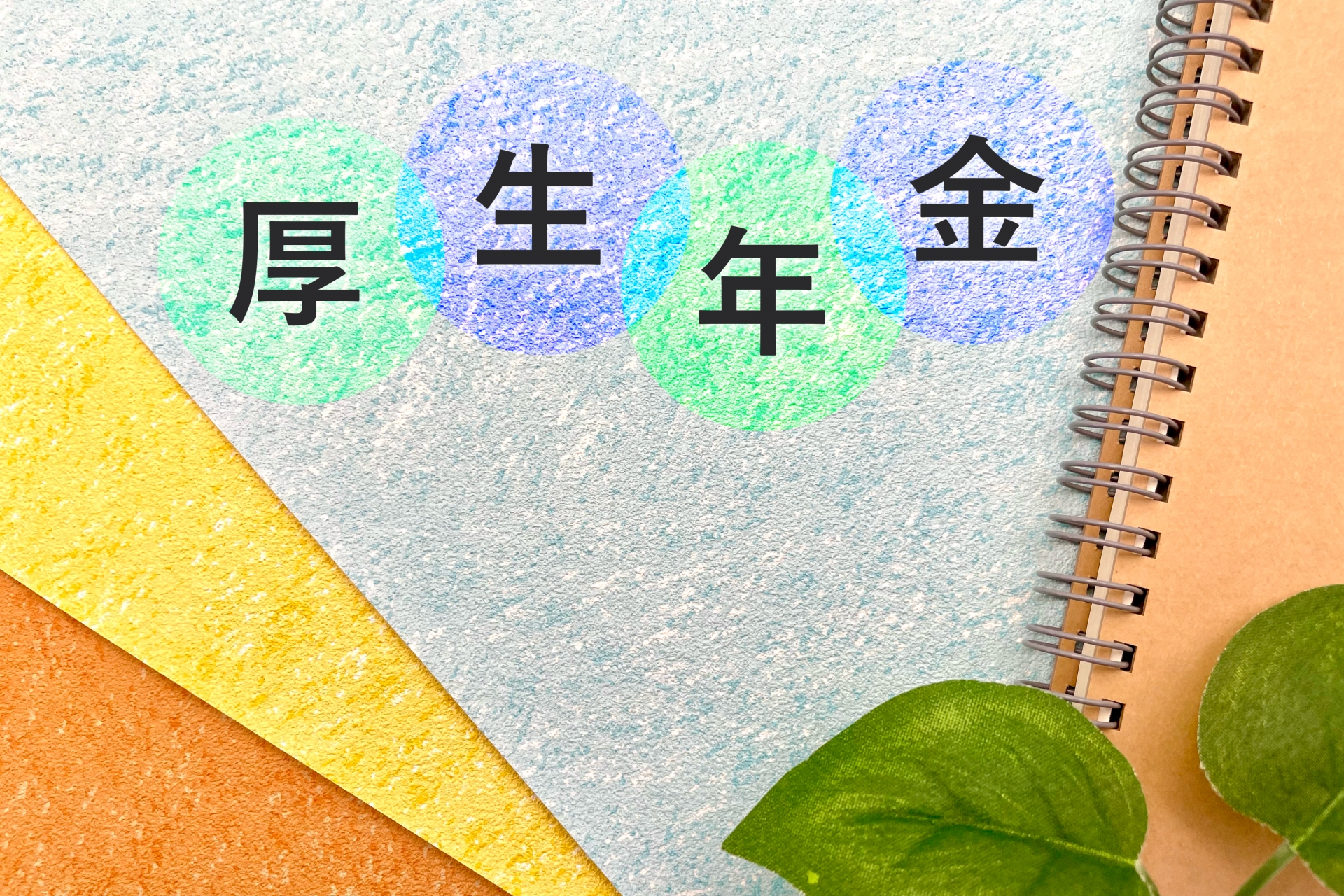2027年9月から厚生年金の保険料が増額されることが決まりました。特に年収798万円以上の会社員は、現在より毎月約9,000円の負担増となります。
- 「給与は増えないのに、手取りが減るの?」
- 「この改正で老後の年金はどう変わるの?」
こうした疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、厚生年金の改正ポイント、在職老齢年金の見直し、将来的な影響、そして対策までをわかりやすく解説します。年金制度の変更をしっかり理解し、今から準備を始めましょう!
厚生年金の保険料が2027年に増額!最新情報まとめ
2027年9月から、年収798万円以上の会社員を対象に厚生年金の保険料が増額されることが決まりました。この改正により、毎月の保険料が約9,000円増えることになります。
これにより「手取りが減るのでは?」と心配する方も多いでしょう。本章では、増額の時期・対象者・具体的な負担額について解説します。
2027年9月から厚生年金の保険料が増額へ
政府は2027年9月から、厚生年金の保険料を引き上げる方針を決定しました。これは、年金財源の安定化を目的としており、高所得者の負担が増える形となります。
✅ なぜ増額されるのか?
- 少子高齢化による年金財源の不足
- 年金制度の維持・強化を目的
✅ いつから適用される?
📅 2027年9月の給与計算分から
影響を受けるのは年収798万円以上の会社員
この増額対象となるのは、年収798万円以上(賞与を除く)の会社員です。
🔹 影響を受ける人の条件
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 対象者 | 年収798万円以上の会社員(賞与除く) |
| 対象人数 | 約168万人 |
ポイント:
📌 会社員のみ対象 → 自営業者やフリーランスは関係なし
📌 年収798万円未満の人は今回の増額対象外
どのくらい負担が増えるのか?(具体的な金額)
増額後の保険料を詳しく見ていきましょう。
| 年収 | 現在の保険料(月額) | 2027年9月以降(月額) | 増額分 |
|---|---|---|---|
| 798万円 | 59,475円 | 68,475円 | +9,000円 |
📌 1年間の負担増:約10万8,000円
📌 10年間負担すると?:総額約108万円
しかし、増額した分は将来の年金額に反映されます。具体的には、10年間支払うと老後の厚生年金が月5,000円増える見込みです。
まとめ
✅ 2027年9月から、年収798万円以上の会社員は厚生年金の保険料が増額
✅ 毎月の負担は約9,000円増加し、年間で約10万8,000円の負担増
✅ 10年間支払うと、老後の年金が月5,000円増加
この改正により、手取りの減少を懸念する人も多いですが、長期的には年金額の増加というメリットもあります。今後の働き方や資産運用を考えるきっかけにしてみてください!
厚生年金保険料の計算方法と今後の変化
厚生年金の保険料は給与に応じて計算され、会社と労働者が半分ずつ負担しています。2027年9月からは、年収798万円以上の会社員を対象に保険料が増額される予定です。
ここでは、計算方法・改定後の負担額・将来の年金額の変化について、わかりやすく解説します。
厚生年金保険料の計算方法とは?
厚生年金の保険料は、「標準報酬月額」×「保険料率」で計算されます。
✅ 計算式
📌 厚生年金保険料(月額)= 標準報酬月額 × 18.3%(労使折半で9.15%ずつ負担)
✅ 標準報酬月額とは?
- 給与(基本給+各種手当)の平均額を一定の区分(等級)に当てはめたもの
- 年1回見直し(毎年9月)
📌 賞与(ボーナス)にも厚生年金保険料が適用される(ただし、今回の改定対象外)
現行の保険料と改定後の比較
2027年9月から、年収798万円以上の会社員を対象に厚生年金の保険料が増額されます。
📊 改定前後の比較(年収798万円以上の場合)
| 年収 | 現在の保険料(月額) | 2027年9月以降(月額) | 増額分(月額) |
|---|---|---|---|
| 798万円 | 59,475円 | 68,475円 | +9,000円 |
📌 年間の負担増 → 約10万8,000円
📌 10年間負担すると? → 総額約108万円
保険料が増えると将来の年金額はどうなる?
「支払う保険料が増えたら、もらえる年金額も増えるの?」と気になるところですね。
✅ 10年間支払った場合の変化
| 負担増総額 | 老後の厚生年金(月額) | 生涯増額分(20年間受給) |
|---|---|---|
| 約108万円 | +5,000円 | 約120万円 |
📌 10年支払うと、老後の厚生年金が月5,000円増額
📌 20年間受給すると、合計120万円増えるため、元は取れる
負担は増えますが、長生きすれば得になる制度とも言えます。
まとめ
✅ 厚生年金の保険料は「標準報酬月額×18.3%」で計算
✅ 2027年9月から、年収798万円以上の会社員は月9,000円の負担増
✅ 10年間支払えば、老後の年金は月5,000円増加し、20年で約120万円のプラス
手取りが減る点はデメリットですが、長期的には受給額の増加につながるため、今からライフプランを考えることが重要です!
在職老齢年金の見直しと高齢者の働き方の変化
2026年4月から在職老齢年金の減額基準が見直され、給与と年金の合計額が月62万円までなら減額されないようになります。これにより、高齢者が働きやすくなると期待されています。
本章では、改正のポイント・影響・今後の年金の変化について詳しく解説します。
2026年4月から在職老齢年金の減額基準が緩和
60歳以上で厚生年金に加入しながら働く人が対象で、給与と年金の合計が一定額を超えると年金が減額される制度です。
✅ 2026年4月の改正内容
📌 現在の基準額:月50万円(給与+年金の合計)
📌 改正後の基準額:月62万円
💡 月62万円までは年金が減額されず、満額受け取れるように!
50万円 → 62万円に引き上げでどんな影響が?
✅ どんな人が影響を受けるのか?
現在、在職老齢年金で年金が減額されているのは約50万人。このうち、約20万人が満額で年金を受け取れるようになります。
📊 改正による影響(例)
| 給与(月額) | 年金(月額) | 現在の支給額 | 改正後の支給額(2026年4月~) |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 22万円 | 42万円(▲5万円減額) | 52万円(満額支給) |
| 40万円 | 25万円 | 50万円(▲7万円減額) | 60万円(満額支給) |
📌 改正後は、給与と年金の合計が62万円未満なら減額なし!
📌 高収入の高齢者ほど、受け取れる年金額が増える
仕事を続ける高齢者の年金はどう変わる?
今回の改正により、高齢者が働き続けるメリットが増えます。
✅ 改正による変化
1️⃣ 働きながら年金を満額受け取れる(月62万円以下なら減額なし)
2️⃣ 年金をもらいながら、将来の年金額も増やせる(厚生年金に加入し続けることで年金が加算)
3️⃣ 企業側も高齢者の雇用を維持しやすくなる
💡 「働くと年金が減るから…」と悩んでいた人も、働きやすくなる!
まとめ
✅ 2026年4月から、在職老齢年金の減額基準が「月50万円→62万円」に引き上げ
✅ 約20万人が満額で年金を受け取れるように!
✅ 給与+年金の合計が62万円未満なら減額なし、働きながら満額受給が可能
高齢者の「働いたら損をする」状況が緩和され、働き続けるメリットが増えます。長く働きたい人にとって、大きな追い風となるでしょう!
年金制度の将来と厚生年金積立金の活用
少子高齢化の影響で、年金制度の財源は厳しくなっています。そこで政府は、厚生年金の積立金を活用して国民年金(基礎年金)を底上げする新たな仕組みを検討しています。
ただし、景気が悪化した場合のみ発動する「経済条項」も設けられる予定です。本章では、この改革の仕組みと影響について解説します。
国民年金(基礎年金)を底上げする新たな仕組み
現在、国民年金(基礎年金)は、主に現役世代の保険料と税金でまかなわれているため、財源が不安定です。
✅ 新たな仕組みのポイント
📌 厚生年金の積立金の一部を国民年金の財源に活用
📌 基礎年金の受給額を底上げし、低所得の高齢者を支援
💡 厚生年金に加入していないフリーランス・自営業者も恩恵を受ける!
厚生年金の積立金はどのように活用される?
厚生年金の積立金(約200兆円)は、将来の年金支払いのために積み立てられている資金です。
✅ 活用方法の変更
| 現行の仕組み | 新たな仕組み(案) |
|---|---|
| 厚生年金加入者の年金給付のために積立 | 一部を国民年金の財源として活用 |
📌 高齢化が進む中で、国民年金を安定化させる狙いがある
📌 ただし、厚生年金の加入者(会社員など)からは「自分たちの年金が減るのでは?」との懸念も
景気停滞時に発動する「経済条項」とは?
厚生年金の積立金を使うには、経済の状況を見ながら慎重に判断する仕組みが必要です。
✅ 「経済条項」とは?
📌 景気が悪化した場合に限り、積立金を活用できるルール
📌 景気が好調なときは積立金を取り崩さない
💡 景気の変動に応じて、柔軟に対応できる仕組みを導入!
まとめ
✅ 厚生年金の積立金を国民年金の財源に活用し、基礎年金を底上げ
✅ ただし、景気が悪いときにのみ発動する「経済条項」を設ける
✅ 厚生年金加入者には「負担が増えるのでは?」という不安も
今後の議論次第で制度の詳細は変わる可能性があるため、引き続き注目が必要です!
厚生年金保険料の増額対策!負担を軽くする方法
2027年9月から年収798万円以上の会社員を対象に厚生年金の保険料が増額されます。手取りが減るため、節約や資産形成が重要になります。
本章では、家計の節約術・企業の対応策・老後資金の準備方法について解説します。
厚生年金の負担増に向けた節約術
✅ 固定費を見直す(すぐに始められる対策!)
- 通信費の削減(格安SIM・プラン見直し)
- 保険の見直し(不要な特約を削る、共済を活用)
- サブスク解約(使っていないサービスを整理)
✅ 税制優遇を活用(節税で負担軽減!)
- ふるさと納税:税控除を受けつつ特産品をゲット
- 医療費控除:年間10万円以上の医療費で確定申告
✅ 支出の管理(家計簿アプリで無駄遣いをチェック)
📌 支出を見える化し、月1万円の削減を目標に!
企業側の対応(報酬制度の見直しなど)
企業も厚生年金の保険料負担が増えるため、以下の対策を検討する可能性があります。
✅ 報酬制度の見直し
📌 現金給与 → 福利厚生(手当)に変更(例:家賃補助、社食など)
📌 賞与を増やし、月額給与を抑える(賞与は今回の改定対象外)
✅ 定年後の働き方を柔軟に
📌 シニア向けの短時間勤務・業務委託の導入
✅ 企業型DC(確定拠出年金)の活用
📌 従業員が将来の年金を増やせるよう、企業型DCを導入
💡 会社員は自社の対応をチェックし、メリットを活用しよう!
個人でできる老後資金の準備方法(iDeCo・NISA活用)
将来の年金不安に備え、税制優遇がある資産形成を活用しましょう。
✅ iDeCo(個人型確定拠出年金)
📌 掛金が全額所得控除され、節税しながら年金を準備
📌 運用益も非課税(60歳まで引き出せないが、その分老後資金に確実に回せる)
✅ 新NISA(2024年開始)
📌 運用益が非課税で、いつでも引き出せる資産形成制度
📌 長期運用に適した「つみたて投資枠」と「成長投資枠」がある
📊 iDeCo vs NISA 比較表
| 項目 | iDeCo | 新NISA |
|---|---|---|
| 税制メリット | 掛金が所得控除 & 運用益非課税 | 運用益が完全非課税 |
| 引き出し | 60歳以降(制限あり) | いつでも可能 |
| おすすめ用途 | 老後資金の確保 | 資産運用・貯蓄 |
💡 NISAとiDeCoを併用し、短期&長期の資産形成をバランスよく!
まとめ
✅ 固定費削減・節税対策で手取り減に対応
✅ 企業の報酬制度変更を活用し、負担を抑える
✅ iDeCo・NISAで老後資金を増やし、将来の年金に備える
今から準備を始めれば、負担増にも柔軟に対応できます。制度をうまく活用して、将来の不安を減らしましょう!
厚生年金の増額と今後の影響まとめ
2027年9月から厚生年金の保険料が増額されます。また、2026年4月には在職老齢年金の減額基準が緩和されるなど、年金制度が大きく変わります。ここまでのポイントをわかりやすくまとめました。
2027年9月から厚生年金の保険料が増額へ
✅ 対象者:年収798万円以上の会社員
✅ 増額額:現在の月5万9,475円 → 約6万8,000円(約9,000円増)
✅ 影響:手取り額が減るが、10年後の年金額は月5,000円ほど増加
📊 厚生年金の保険料増額の比較
| 年収 | 現行(2024年) | 2027年以降 | 増額幅 |
|---|---|---|---|
| 798万円 | 59,475円/月 | 約68,000円/月 | +約9,000円/月 |
厚生年金保険料の計算方法と今後の変化
✅ 計算方法:標準報酬月額 × 保険料率(約18.3%)
✅ 増額の影響:高所得者ほど負担増
✅ メリット:支払額は増えるが、将来の受給額も上がる
在職老齢年金の見直しと高齢者の働き方の変化
✅ 2026年4月から:在職老齢年金の減額基準が「50万円 → 62万円」に緩和
✅ 対象者:現在約50万人 → 20万人は満額受給可能に!
✅ メリット:60歳以上でも働きながら年金を受け取れる可能性が増加
📊 在職老齢年金の変更点
| 現在(2024年) | 2026年4月以降 |
|---|---|
| 50万円超で年金が減額 | 62万円まで減額なし! |
| 減額対象:約50万人 | 約20万人が満額受給可能に |
年金制度の将来と厚生年金積立金の活用
✅ 国民年金(基礎年金)の底上げを検討
✅ 厚生年金の積立金を国民年金に活用する案が浮上
✅ 景気悪化時にのみ実施する「経済条項」を導入予定
📌 年金の安定化を図るが、厚生年金加入者の負担増が懸念される
厚生年金保険料の増額対策!負担を軽くする方法
✅ 家計の見直し(固定費削減・ふるさと納税・節税)
✅ 企業の報酬制度変更(賞与増額・手当の活用)
✅ 老後資金の準備(iDeCo・新NISAを活用)
📊 iDeCo vs 新NISA 比較表
| 項目 | iDeCo | 新NISA |
|---|---|---|
| 税制メリット | 掛金が所得控除 & 運用益非課税 | 運用益が完全非課税 |
| 引き出し | 60歳以降(制限あり) | いつでも可能 |
| おすすめ用途 | 老後資金の確保 | 資産運用・貯蓄 |
💡 増額される厚生年金保険料の負担を減らすために、早めの準備が重要!
まとめ
✅ 2027年9月から厚生年金保険料が増額(年収798万円以上が対象)
✅ 2026年4月から在職老齢年金の減額基準が62万円に緩和
✅ 厚生年金積立金の活用案が浮上(経済条項あり)
✅ 負担増に備えて、節約・資産運用(iDeCo・新NISA)を活用
📌 厚生年金制度は今後も変わる可能性があるため、最新情報をチェックしながら早めの対策を!